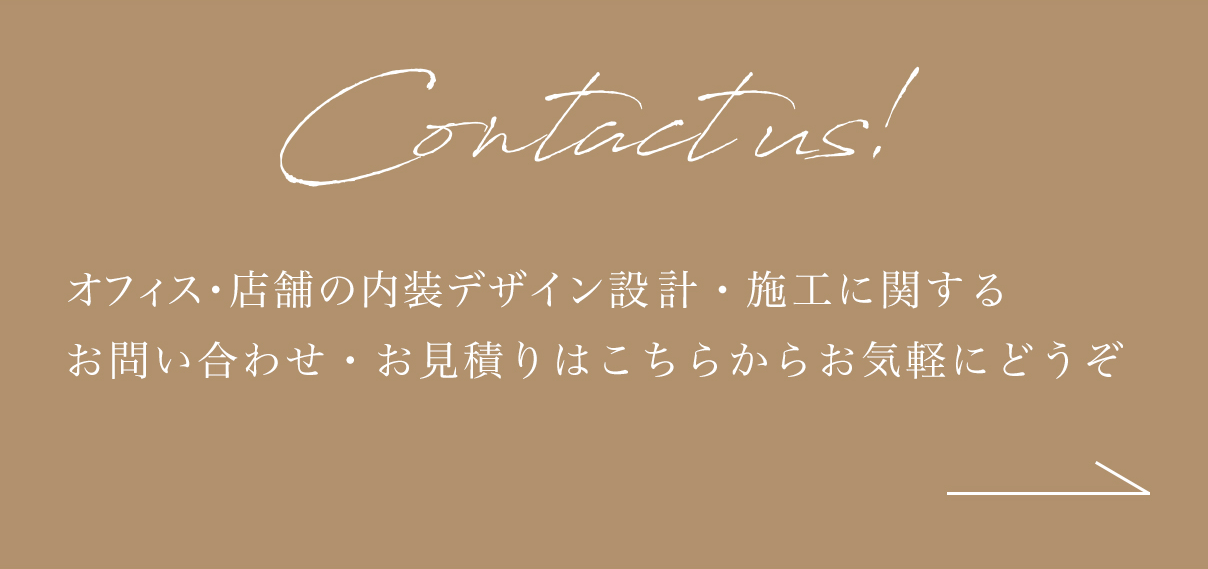オフィス移転の際に行う手続きとは?それぞれの流れについて詳しく解説!

オフィス移転は、企業にとって大きな節目のひとつです。新しい拠点でのスタートは成長の機会となりますが、その一方で、さまざまな手続きや準備が必要になります。解約や契約変更といった社内の対応に加え、取引先や公的機関への届け出も怠ることはできません。
本記事では、オフィス移転時に行うべき手続きをわかりやすく解説し、流れに沿って整理しました。移転を検討している方は、全体像を把握しながら、必要な準備を漏れなく進めていきましょう。
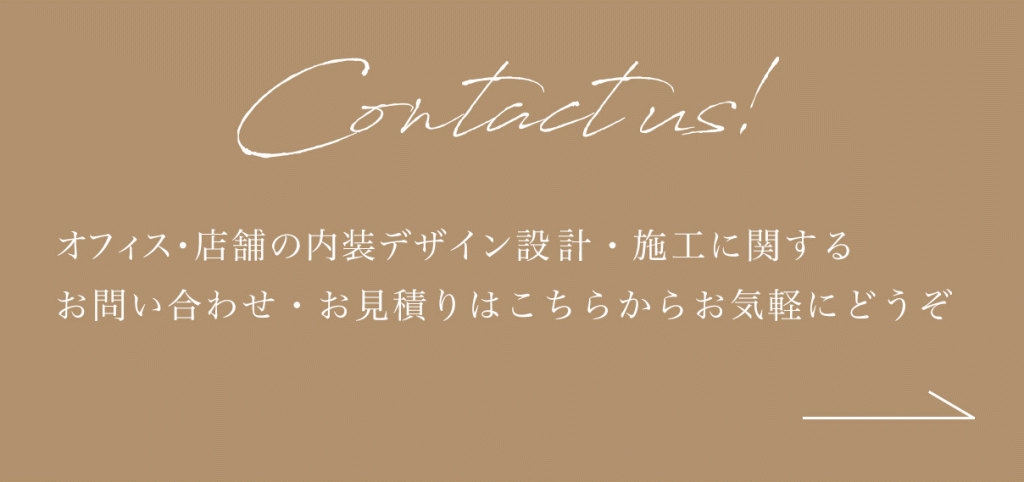
Index
オフィス移転時に必要な手続きとは?

オフィスを移転する際には、現オフィスの契約解除やインフラ回線の変更、金融機関での情報更新など、幅広い手続きが発生します。業務に直結するため、対応が遅れないよう1つずつしっかり対応する必要があるといえるでしょう。
ここでは、オフィス移転の基本的な手続きをひとつずつ解説していきます。
現在のオフィスの解約
オフィス移転を実施する際に最初に行わなければならないステップが、現在利用しているオフィスの解約手続きです。
一般的な賃貸オフィス契約では「解約予告期間」が定められており、多くの場合は3か月から6か月前までに貸主へ通知する必要があります。この期限を過ぎると契約延長扱いとなり、余計な賃料が発生するリスクがあるため注意が必要です。
解約通知を行った後は、原状回復工事の計画も進めなければなりません。オフィス物件では、入居時の状態に戻す義務があるケースがほとんどで、壁や床、配線設備の修繕にかかる費用が高額になることもあります。
そのため、事前に見積もりを取り、予算に反映させておくことが大切です。さらに、退去時には貸主や管理会社による立ち会い確認があり、追加修繕を求められることもあります。こうしたトラブルを防ぐためには、専門業者に相談しながら早めに対応を進めることが有効です。
電話配線やインターネット回線の変更
オフィス移転の際に必ず対応しなければならないのが、電話配線やインターネット回線の整備です。通信環境は日常業務の基盤となるため、準備が遅れると移転後すぐに仕事を再開できず、大きな損失につながる可能性があります。
まず電話回線についてですが、同じ市外局番内であれば現在使用している番号を引き継ぐことができる場合があります。しかし、市外局番が変わる地域に移転する場合は新しい番号を取得しなければならないケースが多く、クライアントや顧客への周知が欠かせません。
次にインターネット回線ですが、こちらはさらに注意が必要です。移転先の建物によって利用可能な回線の種類や速度が異なるため、事前に建物管理会社やプロバイダーへ確認しましょう。特に光回線を新規に敷設する場合は、工事に1〜2か月程度かかることもあります。
また、オフィス規模に応じてLAN配線やWi-Fi環境の設計も必要です。新しいオフィスのレイアウトを考慮し、会議室や執務スペースで安定した通信ができるよう、業者と相談しながら導入を進めることが大切です。
銀行口座やクレジットカードの登録内容の変更
オフィス移転が決まったら、銀行口座やクレジットカードに登録している住所情報の変更も忘れずに行わなければなりません。法人の場合、銀行の登録住所は請求書や振込通知などの送付先として利用されているため、移転直後に早急に手続きを済ませることが望ましいです。
銀行での住所変更は、基本的に口座を開設した支店で行います。必要書類として、移転後の新住所が記載された登記事項証明書や法人印鑑証明書、代表者印などが求められるのが一般的です。手続きをスムーズに進めるために、事前に金融機関へ確認し、必要書類を揃えてから来店するのがおすすめです。
会社名義で利用しているクレジットカードやリース契約中のサービスでも、同様に住所変更が必要となります。法人カードは取引先や仕入れ先への支払いに利用されることが多いため、登録住所が古いままだと請求書の送付先に誤りが生じたり、利用停止となるケースもあります。
オフィス移転は物理的な引っ越しだけでなく、金融関連の情報整備も同時進行で行う必要があります。特に資金の流れに直結する銀行やカードの登録情報は、業務の安定性を守る意味でも最優先で対応しておきましょう。
クライアントへの連絡
オフィス移転の際に最も大切な対外的手続きのひとつが、クライアントへの連絡です。住所や電話番号などの連絡先が変わると、取引先との事務処理や業務連絡に大きな影響を与えます。そのため、移転日が決まった段階で早めに通知を行うことが重要です。
連絡方法としては、まずはメールや郵送による案内状の送付が一般的です。特に重要な取引先や長年付き合いのあるクライアントには、直接訪問して口頭で伝えるとより丁寧な印象を与えることができます。
会社の公式サイトやSNS、ニュースリリースを通じて広く告知することも効果的です。近年はオンラインで情報を得るクライアントが多いため、ホームページの「会社概要」や「お問い合わせ」ページを早急に更新することが欠かせません。
クライアントへの通知は単なる住所変更の案内にとどまらず、「新しい拠点でさらなるサービス向上を目指す」という前向きなメッセージを伝える絶好の機会でもあります。移転を機に関係を強化する姿勢を示すことで、信頼関係をより深めることができるでしょう。
オフィス移転の際の各種公的機関への手続きを徹底解説!

オフィス移転では、契約や社内準備に加えて、公的機関への届け出を確実に行うことが求められます。
法人や個人事業主にとって、税務署・労働基準監督署・公共職業安定所など、複数の機関への手続きが必要となり、それぞれに提出期限や指定書式が定められています。
ここからは、オフィス移転時に必須となる代表的な公的手続きについて、それぞれの内容や流れを詳しく解説していきます。
①労働保険名称・所在地等変更届
オフィス移転を行った場合、まず必要となる公的手続きのひとつが「労働保険名称・所在地等変更届」の提出です。労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた制度であり、企業が従業員を雇用している限り、加入と維持が義務付けられています。
届出は、移転前の所在地を管轄していた労働基準監督署や公共職業安定所に提出するのが一般的です。提出期限は「移転から10日以内」とされており、期限を過ぎると指導の対象になる可能性があります。記載内容は、事業主の氏名や会社名、旧住所と新住所、移転日などで、移転登記の内容と一致していることが求められます。
また、この変更届は単なる形式的な手続きではなく、労働保険料の算定や各種給付の支給に直結します。そのため、社内で担当者を明確にし、移転スケジュールに合わせて優先的に対応することが望ましいです。
労働保険の変更に関する手続きは、社会保険労務士に依頼するケースも多く見られます。専門家に任せることで、書類の不備や提出遅延を防げますから、労働保険関連は外部専門家を活用するのも有効な手段といえるでしょう。
②移転登記申請書
法人がオフィスを移転する際に必ず行わなければならない手続きが、法務局への「移転登記申請」です。会社の所在地は登記事項証明書に記載される基本情報であり、取引先や金融機関からの信頼を支える根幹の一つです。
移転登記の申請先は、新しいオフィス所在地を管轄する法務局です。提出期限は「移転から2週間以内」と定められており、遅れると過料(罰金)が科される可能性があります。
申請には、移転登記申請書、株主総会や取締役会での決議を証明する書類(議事録など)、定款、会社実印、登録免許税の納付などが必要です。登録免許税は資本金の額によって変動し、数万円から数十万円に及ぶ場合もあるため、事前の資金計画に含めておくことが重要です。
特に注意したいのは「管轄外移転」の場合です。例えば、東京都から神奈川県へ移転するようなケースでは、旧所在地と新所在地の両方の法務局に関する手続きが必要になります。手続きが複雑になりやすいため、司法書士に依頼してスムーズに進める企業も少なくありません。
③異動届出書
オフィス移転に伴い、会社や事業所の所在地が変わる場合には、所轄の税務署や市区町村に対して「異動届出書」の提出が必要です。法人税や消費税、事業所税などの課税情報を正確に管理するために欠かせない手続きで、移転後の税務処理をスムーズに行うためにも早めに対応することが求められます。
提出先は、移転後の所在地を管轄する税務署や市区町村の窓口です。提出期限は原則として移転後1か月以内ですが、提出が遅れると税務署から確認や指導を受ける場合があり、場合によっては過料が科されることもあります。
異動届出書は税務署にとって重要な情報源となるため、内容に誤りがあると税務処理に混乱が生じる可能性があります。そのため、提出前には社内で複数人による確認を行うことが望ましいです。
異動届出書の提出は、銀行口座や取引先への登録情報更新のタイミングとも連動します。税務署での届出と同時に、必要な書類を整理し、社内の関係者に周知しておくことで、移転後の業務開始をスムーズに進めることができます。
④事業開始等申告書
オフィス移転に伴い新しい所在地で事業を行う場合、税務署や市区町村に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。この手続きは、法人や個人事業主が新たに事業所を開設したことを正式に届け出るもので、所得税・法人税・消費税などの課税情報を正しく管理するために欠かせません。
提出先は、移転後の事業所所在地を管轄する税務署や市区町村役場です。提出期限は原則として移転後1か月以内ですが、提出が遅れると税務署から問い合わせや指導を受ける可能性があります。
事業開始等申告書は、税務署における課税処理の基礎資料となる重要書類です。情報に誤りがあると、税金の通知や請求書が旧住所に送付されるなど、事務処理の混乱を招く恐れがあります。そのため、提出前には社内で内容をしっかり確認することが大切です。
また、この申告書の提出は、銀行口座や取引先への情報更新、社会保険や雇用保険手続きなど、他の移転関連手続きと同時進行で進めると効率的です。オフィス移転に伴う行政手続きの中でも、特に税務関連の基盤を整える役割を持つため、漏れなく対応することが求められます。
⑤雇用保険事業主事業所各種変更届
オフィス移転に伴い、従業員が加入している雇用保険の事業所情報も更新する必要があります。具体的には「雇用保険事業主事業所各種変更届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出することが求められます。
提出期限は原則として移転後10日以内とされており、遅れると指導や罰則の対象になる可能性があります。届出書には、新しい事業所の名称、所在地、電話番号、事業主名、雇用保険番号などを正確に記入する必要があります。
オフィス移転の際は事業所番号が変更になる場合があり、雇用保険被保険者証や給与計算システムの更新も同時に行う必要があります。これにより、従業員への給付や保険料納付に混乱が生じないようにすることが重要です。
手続きは社会保険労務士に依頼することも可能です。専門家に任せることで、提出書類の不備や記載ミスを防げます。オフィス移転は物理的な引っ越しだけでなく、従業員に関わる各種法定手続きも同時進行で管理する必要があります。
オフィス移転の手続きと同時に考えておくべきことは?

オフィス移転は、契約や公的手続きの処理だけで完了するわけではありません。新しいオフィスでスムーズに業務を開始するためには、セキュリティや防災対策、社内ルールの見直し、オフィスレイアウトの最適化など、多岐にわたる準備が必要です。
移転後の快適な作業環境は社員の生産性に直結するため、単なる物理的な引っ越しではなく、業務効率や安全性も考慮した計画が重要です。ここでは、オフィス移転にあたって手続きと同時に検討すべきポイントを詳しく解説します。
なぜオフィスを移転すべきか
オフィス移転の理由は企業ごとにさまざまですが、主に業務効率の向上やコスト削減、社員の働きやすさを追求するために行われるケースが多いです。
まず、立地の見直しによって通勤時間の短縮やアクセス性の向上が期待できます。これにより社員の満足度や生産性が向上し、離職率の低下にもつながります。また、現オフィスの賃料や維持費が高額である場合、よりコスト効率の良い物件に移転することで経営負担を軽減することも可能です。
業務拡張や新規事業の開始に伴い、従業員数や設備の増加が必要になる場合もあるでしょう。適切な広さやレイアウトを備えた新オフィスへの移転も、成長戦略の一環として重要です。
また、移転を機にオフィス環境を刷新することで、企業のブランドイメージを向上させる効果も期待できます。清潔で機能的なオフィスは、クライアントや来訪者に好印象を与えるだけでなく、社員のモチベーションやチームの一体感を高めることにもつながります。
オフィス移転でルール変更があるか
オフィス移転を行う際には、社内ルールの見直しや変更が必要になる場合があります。例えば、出勤時間やフレックスタイム制度、在宅勤務の運用ルールなど、移転に伴いオフィス環境が変化すると従業員の働き方にも影響が出ることがあります。
特にオフィスのレイアウトやフロア構成が変更される場合、動線や作業効率を考慮した新ルールの策定が求められます。これにより、無駄な移動や混雑を防ぎ、業務効率の低下を防ぐことができます。
セキュリティや情報管理の観点からもルール変更は必要です。入退室管理やデータアクセス権限の見直しを行うことで、情報漏洩リスクを最小化できます。社員へのルール周知は、事前に説明会やマニュアルの配布を行うことで、混乱なく移行が可能です。
セキュリティの見直し
オフィス移転の際には、セキュリティ体制の見直しが非常に重要です。新しいオフィスでは、従業員や来訪者の動線、入退室管理、データ保護の方法など、旧オフィスと異なる環境になることが多く、従来の運用をそのまま持ち込むとリスクが生じる場合があります。
物理的なセキュリティも見直す必要があります。入退室管理システムや監視カメラの設置、鍵の管理方法などを新オフィスの構造に合わせて更新することで、不審者の侵入リスクを低減できます。
クラウドや社内サーバーを利用している場合は、ネットワーク構成やVPNの設定も移転に合わせて確認が必要です。移転に伴う回線変更やIPアドレスの更新を怠ると、業務が一時停止したり、セキュリティ上の穴が生じることがあります。
社員へのセキュリティ教育も重要です。新しい環境に適応したルールや注意点を共有することで、人的ミスによる情報漏洩を防止できます。計画段階からセキュリティ体制を見直し、安全かつ円滑に業務を開始できる体制を整えることが求められるタイミングといえるでしょう。
防災対策の周知と更新
オフィス移転を行う際には、防災対策の見直しと周知も欠かせません。新しいオフィスでは建物の構造や出入口、避難経路が旧オフィスと異なることが多いため、移転前に建物管理者や消防署の指導を参考に、新オフィスに合わせた防災計画を作成することが重要です。
まず、避難経路や非常口、消火器やAEDの配置を確認し、社員に周知します。避難経路の変更は全社員に対して明確に伝え、必要に応じてフロアマップや掲示物を更新することが求められます。
加えて、災害時の連絡方法や安否確認の手順も見直す必要があります。電話やメールだけでなく、チャットツールや社内SNSを活用することで、迅速な情報共有が可能になります。その際、災害時の備蓄品や緊急物資の管理も移転に伴って更新しておくことが望ましいです。
防災対策は社員の安全を守るだけでなく、企業の事業継続性を確保するためにも欠かせません。オフィス移転を機に、最新の情報や状況に応じた対策を整え、全社員に周知することで、安全かつ安心して働ける職場環境を作り上げることができます。
オフィス移転後のレイアウトを考える
オフィス移転では、単に物を運ぶだけでなく、新しいオフィスでの働きやすさや業務効率を最大化するレイアウト設計が非常に重要です。机や設備の配置、会議室や休憩スペースの位置を工夫することで、社員の動線がスムーズになり、業務効率の向上やコミュニケーション活性化につながります。
しかし、自社だけでレイアウトを考える場合、スペースの有効活用や快適性、安全性のバランスを取るのは簡単ではありません。ここでおすすめなのが、オフィスレイアウト設計を専門とする業者の活用です。
その一つである「ヴォーエル」は、企業の業務形態や従業員数に応じた最適なオフィスプランを提案しており、効率的な動線設計や収納スペースの確保、会議室・休憩スペースの配置まで細かくサポートすることが可能です。
さらに、ヴォーエルはセキュリティや防災面も考慮した設計を行うため、安全性を確保しつつ働きやすい環境にも対応しています。プロの知見を活用することで、計画段階から移転後までスムーズに進めることができるでしょう。
オフィス移転後のレイアウト設計は、企業の成長や社員の働きやすさに大きな影響を与えます。プロの支援を受けながら、効率的で快適なオフィス空間を実現することが成功のポイントです。
オフィス移転に困ったならヴォーエルへ!

オフィス移転は、契約手続きや電話・インターネット回線の変更、銀行口座やクレジットカードの情報更新、クライアントへの連絡といった社内外の準備だけでなく、労働保険や雇用保険、登記申請などの公的手続きも同時に行う必要があることをご説明してきました。
オフィス移転に不安のある方におすすめしたいのが、オフィス移転のトータルサポートを提供する「ヴォーエル」です。ヴォーエルでは企業の業務形態や社員数、業務フローを考慮した最適なオフィスレイアウトを提案し、効率的な動線設計やセキュリティ、防災面までトータルにお手伝いいたします。
手続きやレイアウト設計に不安がある場合も、これまで多くのオフィス移転実績のあるヴォーエルの専門的支援を活用いただくことで、計画から移転完了までスムーズに進めることが可能です。オフィス移転を成功させたい企業様は、ぜひヴォーエルにご相談ください。下記ホームページより実際の移転事例をご覧いただけます。