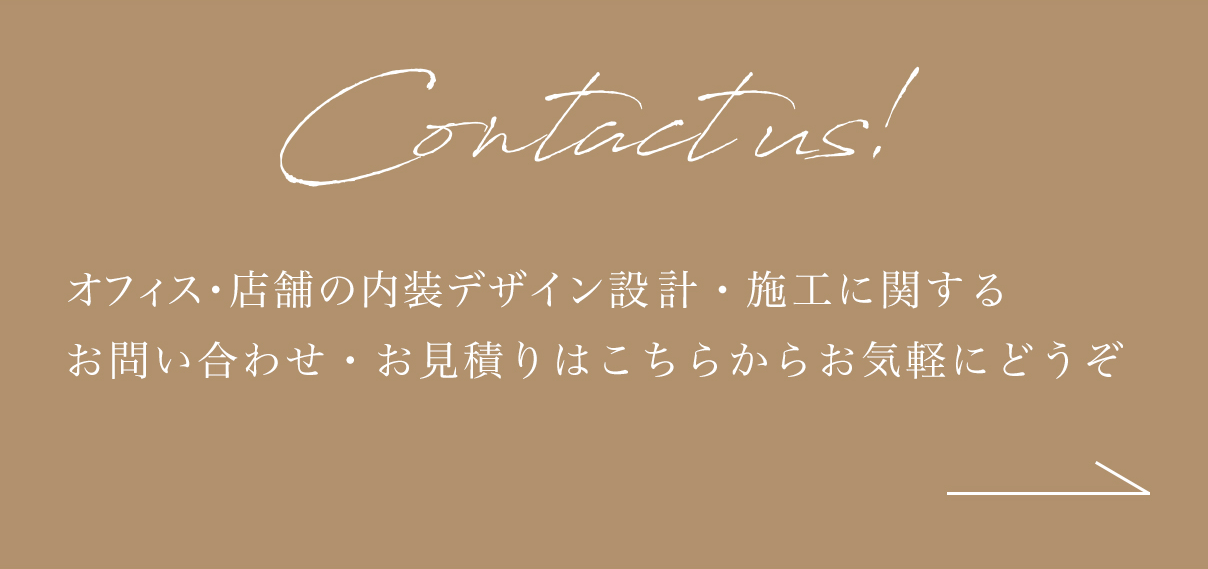仮眠室をオフィスに設置する4つのメリットを解説!設置する際のポイントや運用ルールの決め方も紹介!

オフィスに仮眠室を設ける動きが、働き方改革や健康経営の一環として注目されています。特に長時間労働や業務のパフォーマンス向上が課題となっている企業にとって、仮眠室の導入は重要な施策となり得ます。
本記事では、仮眠室をオフィスに設置するメリットや、設置時のポイント、運用ルールの決め方などを詳しく解説します。
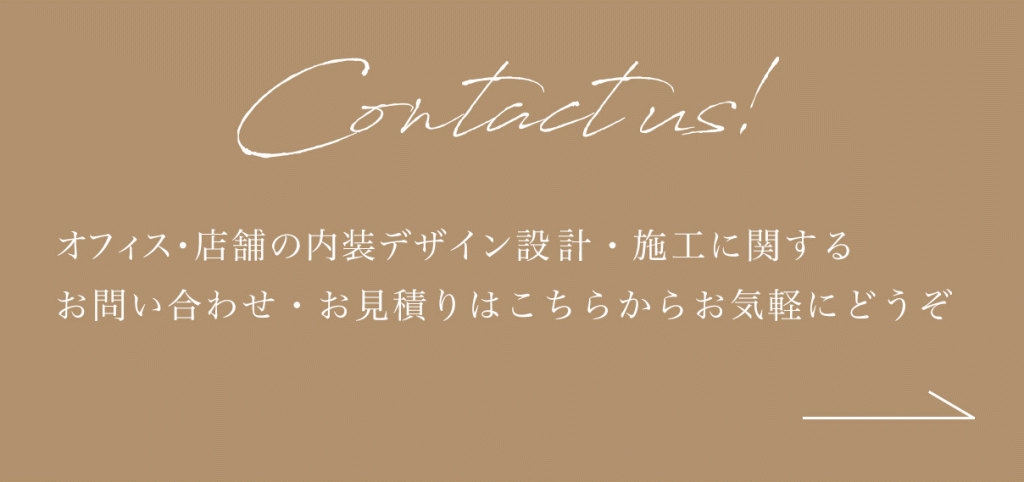
Index
仮眠室を設置するうえで知っておきたい日本人の睡眠事情

日本人の睡眠時間は先進国の中でも特に短いといわれています。OECDの調査によれば、日本人の平均睡眠時間は約7時間弱とされ、健康を維持するには不十分な場合もあります。さらに、ビジネスパーソンの中には6時間以下の睡眠しか取れていない人も少なくありません。このような状況では、日中の眠気や集中力の低下、さらには慢性的な疲労が生産性の低下を招く可能性があります。
企業がこうした睡眠不足に対処する一つの方法として、オフィスに仮眠室を設置することが挙げられます。短時間の仮眠を取ることで、集中力を回復し、午後の業務にも活力をもたらすことができます。睡眠は私生活だけでなく、仕事の質にも大きな影響を及ぼす重要な要素であることを認識することが、企業にとっても従業員にとっても大切です。
仮眠室をオフィスに設置する4つのメリット

オフィスに仮眠室を導入することで、短時間の休息により集中力や判断力が回復し、生産性が大幅に向上します。また、慢性的な睡眠不足による健康リスクを軽減し、社員の心身の健康管理にも寄与します。
専用スペースでは質の高い休憩が可能で、デスクでの仮眠よりも効果的なリフレッシュが得られます。さらに、社員の働きやすさを重視する企業姿勢として、採用活動や企業ブランディングにも良い影響をもたらします。
①生産性の向上につながる
仮眠室を活用することで、短時間の休息を取ることができ、集中力や判断力の回復につながります。特に午後の業務においては、昼食後の眠気によってパフォーマンスが落ちがちですが、20分程度の仮眠を取ることで、脳がリフレッシュし、作業効率が大幅に改善されるケースが多く見られます。アメリカのNASAの研究によれば、26分の仮眠で作業効率が34%向上し、注意力も54%高まったという結果が報告されています。このような科学的根拠からも、仮眠室の有効性は明らかです。
また、仮眠により感情の安定やストレス軽減にもつながるため、社内の人間関係やチームワークの向上にも良い影響を与えます。社員が常にベストなコンディションで働ける環境を整えることが、企業の競争力を高める上で不可欠であることは言うまでもありません。
②社員の健康増進につながる
慢性的な睡眠不足は、うつ病や高血圧、心筋梗塞などの健康リスクを高めるといわれています。仮眠室を用意することで、従業員が意識的に休息を取る習慣がつき、心身の健康管理にもつながります。また、職場でのストレスが軽減されることで、メンタルヘルスの安定にも寄与します。健康経営を実現するうえでも、仮眠室の導入は有効な施策の一つといえるでしょう。
さらに、日々の業務に追われがちなビジネスパーソンにとって、会社が休息の重要性を認識し、そのための空間を提供してくれることは大きな安心感にもなります。従業員の健康を第一に考える企業姿勢は、社内の満足度やロイヤリティの向上にも直結します。
③効果的な休憩が可能
単なるデスクでの仮眠では、十分な休息が得られないことが多く、体がかえって疲れてしまうこともあります。専用の仮眠室であれば、周囲の音や照明を遮断した環境でリラックスした状態で休むことができ、短時間でも質の高い休憩が取れます。これにより、社員は限られた時間でも最大限のリフレッシュ効果を得られるようになります。
とくにIT業界やクリエイティブ業務など、集中力を必要とする職種においては、このような質の高い休憩が作業パフォーマンスに大きく影響します。しっかりとした環境で仮眠を取ることで、午後のパフォーマンスが飛躍的に向上するという声も多く聞かれます。生産性と直結する休憩の質を上げるためにも、仮眠室の整備は非常に有効です。
④会社のブランドイメージが良くなる
仮眠室の設置は、社員の働きやすさや健康を重視する企業姿勢の表れです。そのような福利厚生の整った環境を用意している企業は、求職者にとっても魅力的に映ります。また、社内外へのブランディングにもつながり、「社員を大切にする会社」というポジティブなイメージが定着します。採用活動や企業PRの面でも、仮眠室の導入は良い影響をもたらすでしょう。
最近では、働きやすい職場環境を整えることが採用競争において重要なポイントとなっており、福利厚生の一つとして仮眠室を紹介する企業も増えています。SNSや企業紹介メディアでも話題になりやすく、社内文化を象徴する施策として外部にアピールしやすい点もメリットです。
他にオフィスにあると嬉しい設備が知りたい方はこちら
オフィスにあると嬉しい設備をスペース別・課題別に徹底解説!
仮眠室をオフィスに設置するデメリット

仮眠室の設置は多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。特に導入にあたっては、スペースの確保や初期費用、社員の利用ルールの整備など、現実的な課題に直面することが多いです。また、適切な管理がされない場合、業務効率の低下や不公平感の発生、トラブルの原因になる可能性も否定できません。
ここでは、オフィスに仮眠室を導入する際に考慮すべき主な3つのデメリットについて詳しく解説します。
長時間睡眠をとると生産性が低下する
仮眠は短時間であれば集中力や判断力の回復に効果がありますが、長時間眠ってしまうと逆効果になる恐れがあります。30分を超える仮眠では、深い睡眠に入ってしまい、起床時に強い眠気や倦怠感を伴う「睡眠慣性」と呼ばれる現象が起こります。これにより、仮眠後の作業効率がかえって落ちてしまうことがあります。
また、日中に深く眠ることで夜の本来の睡眠の質が低下し、生活リズムが乱れる可能性もあります。結果として、疲労が蓄積し、パフォーマンスが長期的に低下してしまうおそれも否定できません。
企業として仮眠室を導入する場合は、「仮眠は15~20分程度が最適」といったガイドラインを設けることが重要です。利用者が長時間眠ってしまわないように、アラーム機能付きのチェアやアプリの活用、時間制限ルールなどの対策を講じることが求められます。
残業時間が増えるリスクがある
仮眠室の導入は、社員の生産性や健康維持に貢献する一方で、使い方によっては残業の常態化を助長するリスクもあります。
たとえば、日中に仮眠を取ることで一時的に集中力が高まり、「もうひと頑張りしよう」と思える反面、勤務時間外まで働く社員が増えてしまうケースも見受けられます。
特に長時間労働がすでに常態化している企業では、仮眠室がその状況を正当化する口実となりかねません。また、仮眠後に業務に戻ることで、脳が再び活性化し、結果として退勤時間が後ろ倒しになるといった副作用も考えられます。
企業側としては、仮眠室を「業務効率の向上」と「健康促進」のための施設であると明確に位置づけ、使用目的や時間帯のルールを厳格に定めることが求められます。労働時間管理の徹底と併せて運用することで、仮眠室が逆効果にならないように注意が必要です。
仮眠室をオフィスに設置する際の2つのポイント

オフィスに仮眠室を設置する際には、社員が快適に利用できる環境づくりが重要です。ただ設置するだけでは十分な効果を得ることはできません。周囲の騒音や明るさといった外的要因によって、眠りの質は大きく左右されるため、場所選びや環境整備には細心の注意を払う必要があります。また、仮眠室を導入する目的や社内文化に合った形で整備することが、長期的にうまく活用される鍵になります。
ここでは、仮眠室を設置する際に押さえておきたい2つのポイントをご紹介します。
①執務スペースから離れた場所に設置する
仮眠室をオフィスに設ける場合、最も重視すべき点のひとつが「場所の選定」です。執務スペースと近すぎると、話し声や電話の音、キーボードのタイピング音などが漏れてきて、仮眠中の社員にとって大きなストレスとなります。これでは休息の質が下がってしまい、仮眠の効果が得られません。また、利用者が出入りする際に他の社員の目が気になると、心理的なハードルが高まり、仮眠室が十分に活用されない可能性もあります。
そのため、仮眠室はできる限り執務スペースから距離を置き、静かなエリアに設置するのが理想です。空き会議室やバックオフィスエリア、使用頻度の低いスペースを活用するなどの工夫をすることで、快適な仮眠環境が整います。
②静かで眠りやすい環境を整備する
場所の選定と併せて大切なのが、快適な仮眠環境の整備です。騒音を防ぐために防音パネルを設置したり、遮光カーテンや間仕切りで視界を遮るといった工夫が求められます。また、照明にも配慮が必要で、暖色系の間接照明を採用することでリラックスしやすい空間がつくれます。
室温や湿度の調整も快眠に大きく関わる要素です。さらに、仮眠スペースにはリクライニングチェアや簡易ベッド、アイマスクや耳栓といったリラックスアイテムを備えることで、より質の高い休息が可能になります。衛生面にも配慮し、定期的な清掃や消臭対策を行うことも忘れてはいけません。
このように、物理的な環境だけでなく、利用者が心から安心して仮眠できる空間づくりが重要です。
仮眠室の運用ルールの決め方

オフィスに仮眠室を設置する際には、ただスペースを用意するだけでなく、円滑かつ公正に利用されるような運用ルールを整備することが重要です。ルールが曖昧なままだと、社員間でのトラブルや不公平感が生じ、仮眠室本来の目的である「快適な休息」の場として機能しなくなる可能性があります。
ここでは、仮眠室の利用にあたって特に留意すべき3つのルールについて解説します。
次に使う人が気持ちよく使えるようにする
仮眠室は複数の社員が共用するスペースであるため、マナーや清潔感を保つことが何より大切です。たとえば、使用後にはブランケットや枕の位置を整えたり、リクライニングチェアを元の位置に戻したりするなど、次に使う人への配慮を欠かさないことが求められます。
また、汗をかいたり、匂いが気になる場合は備え付けの除菌シートや消臭スプレーで清掃するなど、最低限の衛生管理もマナーのひとつです。
このような利用ルールを明文化し、社内に周知徹底することで、誰もが気持ちよく使える仮眠室となり、社内のエンゲージメント向上にもつながります。
音の大きさに注意する
仮眠室では静けさが重要です。携帯電話の通知音や話し声、ドアの開閉音などが気になって眠れないという社員も少なくありません。したがって、仮眠室内ではマナーモードを徹底すること、会話を控えること、静かに出入りすることなど、音に関するルールを明確にしておく必要があります。
可能であれば、入口には「静かにしてください」といったサインを掲示するのも有効です。また、仮眠スペースの周囲にも静音対策を施すことで、環境全体の快適性を高めることができます。利用者全員が音に対する意識を持つことで、質の高い休息が取れる環境が維持されます。
利用時間を定める
仮眠の効果を最大限に引き出すには、利用時間を適切に制限することが不可欠です。前述のとおり、長時間の仮眠は「睡眠慣性」によりかえって眠気や集中力の低下を招くことがあります。最適な仮眠時間は15〜20分程度とされており、それを超えないようにルールを設けるのが理想的です。
また、利用者が集中する時間帯を避けるために、予約制やシフト制を導入することも有効です。仮眠室の利用履歴を記録し、適切な運用が行われているかを定期的に確認することも、長期的なルール運用の安定につながります。時間管理を徹底することで、公平かつ効率的な仮眠室の活用が実現します。
仮眠室に置くと良いものや設備

仮眠室の効果を最大限に高めるには、快適に休息できる環境を整えることが不可欠です。特に、リラックスを促す家具やアイテムの導入は、短時間でも質の高い仮眠を実現するうえで重要な役割を果たします。
ここでは、仮眠室に設置することで利便性や快適性が向上するおすすめの設備やアイテムを4つご紹介します。
リクライニングソファ
リクライニングソファは、仮眠室における代表的な家具のひとつです。背もたれの角度を自由に調整できるため、使用者が最も快適と感じる姿勢で休息を取ることができます。座面や背面に適度なクッション性があるソファを選べば、短時間の仮眠でも身体への負担が少なく、リフレッシュ効果をより感じやすくなります。
また、収納式のフットレスト付きソファであれば、足を伸ばして全身を休めることも可能です。コンパクトなタイプも多く販売されており、限られたスペースでも設置しやすい点もメリットです。
ホワイトノイズ
ホワイトノイズとは、一定の周波数で構成された「サーッ」という雑音で、周囲の音を打ち消すように働きます。これを仮眠室に導入することで、オフィスの騒音や外部の物音を軽減し、落ち着いて眠れる環境をつくることができます。
特に、完全な防音が難しい場所に仮眠室を設ける場合には、ホワイトノイズマシンやスマートスピーカーに専用の音源を再生させる方法が有効です。心地よい音のなかで仮眠を取ることができるため、入眠までの時間も短縮され、短時間でも深い休息が可能になります。
アイマスク
アイマスクは、まぶしさを遮って視覚からの刺激を減らし、リラックス状態へと導いてくれるアイテムです。仮眠室に遮光設備を整えていても、完全に暗くするのは難しいことが多いため、個人単位で使用できるアイマスクは非常に有効です。特に、立体構造や低反発素材を採用したアイマスクであれば、目元に圧迫感がなく、より快適に装着できます。
ラベンダーなどのアロマ付きアイマスクもあり、香りの効果によって入眠しやすくなる場合もあります。利用者が自由に使えるよう、常備しておくとよいでしょう。
耳栓
耳栓は、周囲の物音を遮断し、静寂な環境をつくり出すために効果的なアイテムです。特にオフィス内での雑音や空調の音が気になる場合に、耳栓を使うことでストレスを軽減し、スムーズな入眠が期待できます。
フォームタイプの耳栓であれば、耳にやさしくフィットし、長時間の使用でも違和感が少ないためおすすめです。衛生面にも配慮し、使い捨てタイプや個包装された耳栓を準備しておくと、より多くの社員が安心して利用できるでしょう。
ヴォーエルによるオフィスの施工事例

実際に仮眠室や快適な休憩スペースを導入している企業の事例を知ることで、自社に取り入れる際の具体的なイメージを掴むことができます。
ここでは、オフィスデザインを手がけるヴォーエル株式会社が設計・施工を行った3つの事例をご紹介します。どの事例も、社員の生産性向上や働きやすさに貢献している点が注目されています。
株式会社クオンテックス東京オフィス
大阪本社の移転プロジェクトに続き、株式会社クオンテックス様より東京オフィスの拡大移転における内装デザインをお任せいただきました。
全体の設計方針として、ベースカラーをシンプルに統一し、特徴的なデザイン要素が効果的に映える空間づくりを心がけました。オフィス中央部に配置したリフレッシュエリアでは、オリジナルの大型造作ソファを設置し、足元への間接照明配置とフェイクグリーンの効果的な配置により、印象的で存在感のある憩いの場を創出しています。
空間設計の特徴として、各エリアを区切る間仕切りに直線だけでなく、斜めのラインやアール形状を巧みに組み合わせ、視覚的な変化と動きを演出しました。さらに大型ガラスパネルの採用により、物理的な境界を保ちながらも視覚的な広がりと開放感を実現。
照明計画では、メイン照明に加えてブラケットライトや間接照明を戦略的に配置し、空間に豊かな陰影と奥行きを生み出すことで、温かみがありながら洗練された落ち着いた空間に仕上げました。
石井食品株式会社
「日本一、生産者と地域に貢献する食品会社になる」という企業理念を掲げる石井食品株式会社様の大阪オフィス移転プロジェクトを、弊社グループ会社との協働により担当させていただきました。
デザインコンセプトの核心は、企業の持つ多面性の空間表現です。創業から現在まで時代の変化に対応してきた柔軟性と、様々なライフシーンを支える親しみやすさを、流れるようなアールの曲線で表現。対照的に、老舗ベンチャーとして培ってきた挑戦精神や、品質への揺るぎないこだわりと誇りは、力強い直線的デザインで視覚化しました。この相反する要素の調和により、現在の石井食品ブランドの本質を空間に込めています。
エントランスデザインでは、自然の土を連想させるジョリパット左官仕上げの壁面により、温かみのある雰囲気と地域への貢献イメージを同時に表現。土や緑といった自然色を基調とした色彩計画と、各所に配した間接照明の陰影効果により、信頼感を醸し出す上質な空間を実現しました。執務エリアも同様の色調で統一感を保ちながら、フェイクグリーンやアクセントクロスを効果的に配置し、従来の事務所的な印象を払拭した心地よいワークスペースが完成しています。
三栄鋼材株式会社東京事務所
鋼材分野におけるトータルソリューションを提供する三栄鋼材株式会社様。大阪本社・東京事務所の改装に続き、東京事務所の拡大移転という新たな節目において、再びご信頼をいただき内装工事を担当いたしました。
空間デザインの最重要課題は、限られた面積での最大限の開放感創出でした。エントランスでは透明なガラス間仕切りを効果的に配置し、廊下奥のスペースまでを一体的な空間として取り込む設計手法を採用。奥の壁面にはコーポレートカラーのブルーを施し、手前のガラス面には透明感のある「イロミズ」カラーシートを貼付した上に会社サインを設置することで、視覚的な奥行きと印象的なブランディング効果を同時に実現しています。
空間の機能分化にも配慮し、来客エリアでは天然木突板の温もりと大型ガラス面の開放感を組み合わせ、落ち着きと上質感を両立した雰囲気を創出。一方、執務エリアは清潔感のある白を基調とし、各部署の業務特性に応じた適切なゾーニング計画により、機能性と快適性を兼ね備えた効率的なワークスペースを完成させました。
オフィスに仮眠室を設けるならヴォーエルへ

オフィスに仮眠室を設けることは、社員の集中力回復や生産性向上、健康維持といった多くのメリットをもたらします。ただし、その効果を十分に発揮するためには、設置場所や設備、運用ルールの整備が欠かせません。特に、リクライニングソファやホワイトノイズ、アイマスク、耳栓といったアイテムの導入は、快適な仮眠環境の構築に大きく寄与します。
さらに、実際の施工事例からも分かるように、社員が安心して休める空間づくりにはデザインと運用の工夫が求められます。仮眠室を上手に活用することで、働きやすい職場環境が整い、企業全体の活力向上にもつながるでしょう。
仮眠室の設置を含めたオフィス環境の改善をお考えの際は、ぜひヴォーエルにご相談ください。専門的な知識と豊富な経験を持つスタッフが、企業様のニーズに合わせた最適な提案を行い、快適で機能的なオフィス空間の実現をサポートいたします。
詳細は、株式会社ヴォーエルの公式サイトをご覧ください。