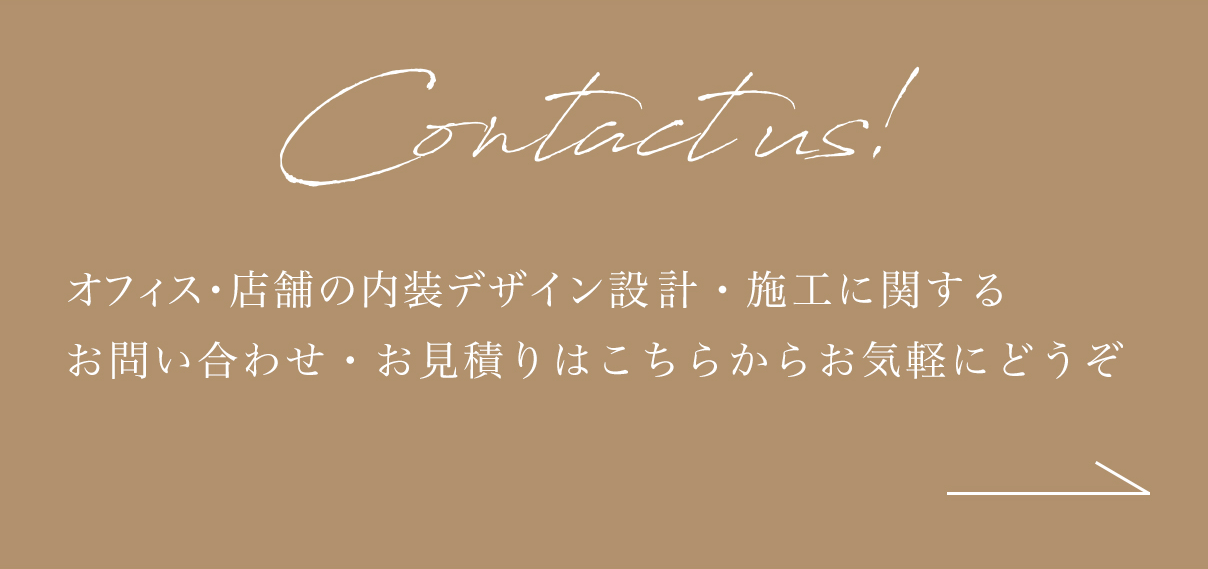オフィス移転で使える補助金とは?費用を抑える制度や申請の流れについて徹底解説!
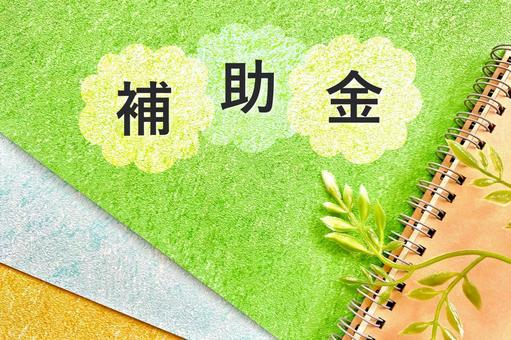
オフィスを移転する際には、賃貸契約の初期費用や内装工事、引っ越し代金など、まとまったコストが発生します。とくに中小企業やスタートアップにとっては大きな負担となるため、費用を少しでも軽減できる方法を知っておきたいところです。その一つが、国や自治体が提供している補助金や助成金の活用です。
本記事では、オフィス移転において利用できる補助金や助成金の種類、その違い、実際の申請方法や注意点について詳しく解説します。さらに、移転を検討する企業に向けて、制度を効果的に活用するための流れも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
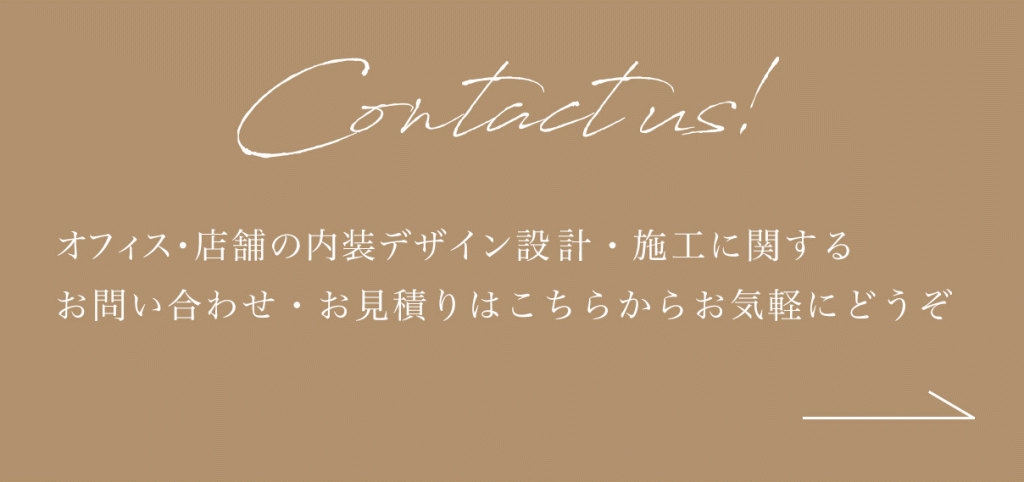
Index
オフィス移転で費用の軽減ができる補助金とは?

オフィス移転の際には「補助金」と呼ばれる制度を利用することで、大きく費用負担を抑えることが可能です。補助金は、国や地方自治体が特定の取り組みを支援するために交付する資金であり、一定の条件を満たすことで返済不要で受け取れます。
ただし、補助金は「審査制」であり、すべての企業が必ず受け取れるわけではありません。ここからは、オフィス移転に関連して利用が検討できる代表的な補助金制度について解説していきます。なお申請期間や条件等はそれぞれ異なるため、申請時の最新情報は各公式サイトでご確認ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が一定規模以下の事業者を対象とし、販路開拓や業務効率化を支援する制度です。
オフィス移転においては、移転先での事業拡大や新たな設備導入が「販路開拓」や「生産性向上」に位置づけられる場合、対象経費として認められる可能性があります。新オフィスに合わせてホームページを刷新する費用や、営業活動に直結する什器・機材の導入なども申請できる場合があります。
補助金額は最大50万円程度(特例により100万円以上のケース・インボイス特例あり)で、補助率は2/3が一般的です。申請には商工会議所や商工会のサポートを受けることが必須で、事業計画書の作成から申請までを伴走してもらえる点も特徴です。
採択されるためには、移転が単なる引っ越しではなく「事業の発展につながる取り組み」であることを示す必要があります。移転を機にビジネスを広げたいと考える小規模事業者には、とくに相性が良い補助金です。
※参考:小規模事業者持続化補助金
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響や社会環境の変化を踏まえ、企業が大胆な事業転換を行う際に活用できる代表的な制度です。単なるオフィスの引っ越し費用を支援するものではなく、「新しい事業の立ち上げ」「業態転換」「新市場への進出」といった成長戦略に直結する取り組みが対象となります。
補助金の規模は非常に大きく、中小企業の場合でも最大で数千万円規模にのぼるケースがあります。補助率も1/3~3/4と手厚く、移転に伴う内装工事費や設備投資、デジタル化に必要なシステム導入なども対象に含まれる可能性があります。
ただし、採択率は決して高くなく、申請には詳細かつ実現可能性の高い事業計画が必須です。単なるコスト削減や移転の合理化ではなく、「なぜその移転が事業再構築に必要なのか」を説明できなければ採択は難しいでしょう。
この補助金を活用できれば、オフィス移転を大きな成長戦略の一部として進められるため、企業にとっては非常に魅力的な選択肢となります。移転を契機に新しい市場へ踏み出したい、働き方を刷新したいと考える経営者にとっては、まさに挑戦を後押ししてくれる制度といえるでしょう。
※参考:事業再構築補助金
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的なサービスや製品を生み出すための投資を支援する制度です。名前のとおり製造業のイメージが強いですが、実際には幅広い業種で活用可能であり、オフィス移転に関連する設備投資やシステム導入にも利用できるケースがあります。
補助金額は100万円から最大で数千万円規模にのぼり、補助率は最大で2/3と高水準です。オフィス移転に伴う内装工事そのものは対象になりにくいものの、移転に合わせて導入する最新機材、業務効率化のためのシステム、または研究開発環境を整えるための投資などは対象になる可能性があります。
注意点として、ものづくり補助金は「新規性」と「成長性」を特に重視しており、平凡な計画では採択されにくい傾向にあります。採択されるためには、移転後の環境でいかに新しい価値を生み出せるかを事業計画に落とし込むことが必要です。
※参考:ものづくり補助金総合サイト
IT導入補助金
IT導入補助金は、オフィス移転そのものへの補助ではなく中小企業や小規模事業者が業務効率化やデジタル化を進めるために必要なITツールの導入費用を支援する制度です。
オフィス移転の際には、移転先での業務体制を一新する絶好の機会であり、このタイミングでITシステムを導入することで補助金の対象となることがあります。クラウド型の会計ソフト、顧客管理システム(CRM)、勤怠管理システム、在宅勤務に対応するグループウェアなどが補助対象ツールとして認められています。
補助額は数万円から最大450万円程度まで幅があり、補助率は1/2程度が一般的です。また、通常のIT導入だけでなく、サイバーセキュリティ対策やインボイス制度対応ソフトなど、時流に合ったシステム導入もカバーしています。
ただし、「IT導入支援事業者」と呼ばれる登録ベンダーを通じて申請する必要があり、自社単独での申請はできません。そのため、移転計画と並行してベンダーを探し、相談しながら計画を進めることがポイントとなります。
※参考:IT導入補助金
創業者向け補助金・給付金
創業者向け補助金・給付金は、国や自治体が新たに事業を立ち上げる起業家やスタートアップを支援するための制度です。
オフィス移転は、創業期に初めて拠点を構える場合や、事業拡大のために拠点を広げる場面でよく発生します。その際に必要となる賃料や内装工事、設備投資などの一部を補助してもらえる可能性があるのが、この制度の大きな魅力です。
国の制度としては「創業補助金(地域創造的起業補助金)」などがあり、補助率は最大で2/3、補助額は数百万円に及ぶこともあります。自治体ごとに独自の創業支援制度が設けられており、賃料補助や従業員雇用に伴う助成が受けられるケースもあるため、調べてみるに越したことはありません。
注意点は、創業期の補助金は「事業計画の実現性」と「地域経済への貢献度」といった点が重視されることです。移転を通じてどのように事業を成長させるのかを具体的に説明することが不可欠であり、単なる事務所確保では申請が通りにくい傾向があります。
※参考:創業者向け補助金・給付金(都道府県別)
※東京の場合はこちら:創業助成金(東京都中小企業振興公社)
移転でもらえる費用の助成金と補助金の違いを解説!

オフィス移転の際に利用できる制度には「助成金」と「補助金」があります。どちらも返済不要で企業を支援する仕組みですが、内容や申請方法、受け取りやすさには大きな違いがあります。
混同されがちですが、この違いを正しく理解しておかないと「申請したのに対象外だった」といったトラブルになりかねません。ここからは、両者の特徴を詳しく解説します。
助成金
助成金は、主に厚生労働省や地方自治体が管轄し、企業の雇用促進や労働環境の改善を目的として支給される制度です。最大の特徴は「要件を満たせばほぼ受け取れる」という点にあります。
オフィス移転との関係で考えると、新拠点での人材採用や雇用環境の改善に取り組む場合に助成金が使えるケースがあります。例えば「キャリアアップ助成金」は非正規雇用を正社員化した際に支給されるもので、新オフィスで人員体制を強化する際には有効です。
金額は数十万円から数百万円程度で、補助金と比べると規模はやや小さめですが、受け取りやすさを考えれば魅力的です。ただし、助成金には必ず「目的」が設定されており、その趣旨に沿った取り組みを行わなければ支給されません。
オフィス移転そのものを直接支援するわけではないものの、移転と同時に人材確保や労働環境改善を進めたい企業にとっては、助成金は現実的かつ取り組みやすい制度だといえます。
補助金
補助金は、経済産業省や中小企業庁、自治体などが提供する制度で、企業の新規事業展開や生産性向上、設備投資などを支援する目的で交付されます。助成金と違い、こちらは「審査制」であり、応募しても必ず受け取れるとは限りません。
オフィス移転の場面では、補助金のほうが直接的に費用削減につながるケースが多いです。例を挙げると「事業再構築補助金」では新たな事業展開を目的とした移転費用や内装工事費、「IT導入補助金」では移転に合わせたシステム導入費などが対象となります。
ただし、補助金は申請手続きが煩雑で、採択率も決して高くはありません。さらに、採択後に交付される「後払い方式」であるため、一度は自社で費用を立て替える必要があります。また、事業報告や成果の提出も義務付けられており、申請から受け取りまでに半年以上かかることも珍しくありません。
その分、補助金を活用できれば企業にとって大きな資金的メリットがあります。オフィス移転を単なる引っ越しではなく「成長戦略の一環」として位置づけ、事業計画に落とし込むことで補助金を得られる可能性は高まります。
オフィス移転で申請できる助成金についても紹介!

オフィス移転においては、補助金だけでなく「助成金」が活用できるケースもあります。助成金は主に労働環境の改善や雇用促進を目的とした制度であり、一定の条件を満たせば原則として支給されます。
自治体によっては創業期の事業者向けの助成制度が用意されており、初めてのオフィス開設や拠点拡大を後押ししてくれます。ここでは、代表的な助成金である「キャリアアップ助成金」と「創業助成金」について解説しましょう。なお年度によって条件等が異なるため、いずれも最新情報をご確認ください。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者の待遇改善や正社員化を推進するために厚生労働省が実施している制度です。オフィス移転との関係で考えると、新しい拠点で人員体制を強化したり、従来の契約社員・パート社員を正社員化する際に利用できる点が注目されます。
対象となる取り組みは幅広く、非正規社員を正社員に転換するケースのほか、処遇改善やスキルアップのための教育訓練を実施する場合にも適用されます。助成金額は1人あたり数十万円から、取り組み内容や条件によっては数百万円規模になることもあり、企業にとって大きな支援となります。
申請の際には、雇用契約書や就業規則、賃金台帳などの整備が必要です。また、対象となる正社員化や処遇改善は「移転前に決定していた取り組み」ではなく、制度開始以降に新たに行うものに限られる点に注意が必要です。
オフィス移転を「組織の拡大や人材強化のタイミング」と捉える企業にとって、キャリアアップ助成金は資金面の後押しとなるだけでなく、雇用の安定化にもつながる制度といえるでしょう。
※参考:厚生労働省 キャリアアップ助成金
創業助成金
創業助成金は、これから新たに事業を立ち上げる起業家やスタートアップを支援するための制度です。国の制度だけでなく、自治体ごとに独自の助成金が用意されており、オフィス移転というより「オフィス新設」に直結するケースが多いのが特徴です。
助成対象は、賃料や内装工事費、人件費、設備投資など幅広く設定されています。助成率は2/3程度、助成額は数百万円に及ぶこともあり、起業家にとっては大きな資金的支援となります。特に東京都の「創業助成事業」では、最大300万円までの支援が受けられるため、首都圏で起業を考える人に人気の制度です。
申請の際には、事業計画書の提出や将来的な収支予測の提示が求められます。補助金と同様に審査が行われるため、必ず採択されるわけではありませんが、助成金であるため採択後のフォロー体制が比較的充実しているのも特徴です。
創業助成金をうまく活用できれば、オフィス開設の初期費用を大きく軽減でき、安心して事業をスタートさせることができます。創業期の限られた資金を有効に活用したい起業家にとって、見逃せない制度といえるでしょう。
※参考:創業者向け補助金・給付金(都道府県別)
※東京の場合はこちら:創業助成金(東京都中小企業振興公社)
移転費用のための補助金を利用する際の注意点とは?

オフィス移転の際に補助金を利用することで、費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。しかしながら、補助金は「ただ申し込めばもらえるお金」ではなく、制度の特性を理解し、十分な準備を整えてから活用しなければなりません。
ここからは、補助金を利用する際に特に気をつけたい代表的なポイントを一つずつ解説していきます。
手続きが複雑になる
補助金の利用で最も多くの企業が直面する壁が「手続きの煩雑さ」です。オフィス移転に関する補助金を申請する際には、事業計画書や収支計画、見積書や契約書など、多岐にわたる書類を作成・提出する必要があります。
さらに申請書類の内容は詳細かつ正確でなければならず、単なる「移転費用の補填」ではなく「事業の発展や競争力強化につながる投資」であることを明確に説明することが求められます。
この過程では、事業目的や移転後の効果を論理的に示すプレゼンテーション能力が必要になり、経営者だけで対応するのは負担が大きいケースも少なくありません。採択された後も、交付決定通知や実績報告、経費証憑の保存・提出など、複数の段階を経る必要があります。
そのため、補助金の申請は「単なる経費削減策」ではなく、会社全体の経営戦略や財務管理の一部として位置づける必要があります。中小企業診断士や商工会議所、金融機関、行政書士といった外部専門家にサポートを依頼することで、作業負担を減らしつつ申請精度を高める方法も有効です。
頻繁に更新される
補助金制度は国や自治体の方針や予算状況によって柔軟に変更される仕組みであるため、年度や時期によって内容が変動する点に注意が必要です。
例えば、ある年度には「生産性向上」や「IT活用」が重点テーマとなっていたのに、次の年度には「脱炭素」や「地域活性化」が重視されるなど、制度の目的がガラリと変わることがあります。
これに伴い、対象経費や補助率、上限額も見直されるため、過去の情報だけを頼りにすると申請の段階で「対象外」と判断される可能性が出てきます。
したがって、補助金を活用する際には「最新情報のチェック」が欠かせません。経済産業省や中小企業庁、各自治体の公式サイトを定期的に確認したり、商工会議所や金融機関のセミナー情報を活用したりするのが有効です。
できるだけ早く申請する
補助金は「予算に上限がある」という性質を持っているため、申請が殺到すれば早期に打ち切られる場合があります。特に自治体が実施する補助金には先着順で採択される制度も存在するため、のんびり準備しているとせっかくのチャンスを逃してしまうリスクが高まります。
補助金の審査は応募が多くなるほど競争率が上がり、採択されにくくなるでしょう。早めに申請すれば、審査側に余裕がある時点で評価されるため、結果的に採択率を高められる可能性もあります。
準備を前倒しで進めるためには、まず利用できそうな補助金の情報を早い段階で集め、応募要件を確認することが大切です。その上で、申請に必要な書類を事前に作成・確認し、スケジュールの余裕を持たせることが成功へのポイントになります。
後払いのため立替が必要
補助金の多くは「後払い方式」で交付される点に注意が必要です。つまり、オフィス移転にかかる内装工事費や設備費、引っ越し費用などは、まず企業自身で全額を支払う必要があります。その後、必要書類を揃えて申請し、補助金が交付されるという流れです。
特に中小企業やスタートアップの場合、資金に余裕がない状態で大規模な移転を行うと、支払い遅延や銀行借入の追加など、想定外の負担が生じることがあります。そのため、補助金の受給を前提にした移転計画を立てる場合には、事前に資金計画を緻密に作成し、必要に応じて銀行融資やリース契約を活用することが不可欠です。
経費として計上する際には、領収書や契約書などの証憑を整備しておく必要があります。後払い方式の性質を理解し、資金面での余裕を確保しておくことは、スムーズに補助金を活用する上で大変重要です。
課税対象になる
補助金は返済不要で受け取れるため、経営者にとって魅力的な資金源ですが、実は「課税対象」になる場合があります。受け取った補助金は法人税や所得税の課税対象となり、会計処理や税務申告に影響を与えることもあるでしょう。
補助金を受け取った後の手取り額と実際にかかる移転費用の差を見誤ると、資金計画にズレが生じることがあります。課税のタイミングや計上方法も補助金の種類や会計基準によって異なるため、事前に税理士や会計士に相談して正しい処理方法を確認しておくことが必須です。
補助金を有効に活用するためには、税務上の取り扱いを正しく理解し、事前に計算した資金繰りに組み込むことが欠かせません。オフィス移転を進める前に、課税の影響も考慮した計画を立てることが、補助金活用の成功につながります。
返さないといけない場合がある
補助金は基本的に返済不要ですが、条件を満たさなかった場合や不正があった場合には返還義務が生じます。申請内容と異なる用途で資金を使用した場合や、経費証憑の不備、申請書類の虚偽記載があった場合には、補助金の全額または一部を返還しなければならない可能性があります。
補助金の交付後も、一定期間は事業の状況報告が必須の義務です。この報告に不備があると、後から返還を求められることもあるため、事務処理や証憑管理を徹底して行う必要があります。
そのため、補助金の申請前には、返還条件や必要な手続き、管理方法をしっかり把握しましょう。オフィス移転の計画と補助金の条件を照らし合わせ、返還リスクを最小限に抑える管理体制を構築することが、安心して制度を活用するためのポイントです。
オフィス移転で補助金がもらえるまでの申請の流れについて詳しく解説!

オフィス移転に伴う補助金を利用する場合、単に申請書を提出すればすぐに受け取れるわけではありません。制度の種類や条件に応じて、申請のステップを正しく踏むことが必要です。
それぞれの段階でポイントや注意点がありますので、ここでは申請から受け取りまでのステップを順に解説します。
申請できる補助金を見つける
最初のステップは、自社のオフィス移転に適した補助金を見つけることです。国や自治体が実施する補助金は種類が多く、対象業種や経費の範囲、補助率、補助金額などが異なります。
事業再構築補助金やIT導入補助金、ものづくり補助金など、それぞれ目的や条件が違います。こうした点を踏まえ、移転費用を補助対象にできるかどうかを確認することが重要です。
調べる方法としては、公式サイトの公募要領をチェックするのが基本です。公募要領には、対象事業、対象経費、申請期間、提出書類、採択基準などが詳細に記載されています。
これに加え、商工会議所や中小企業診断士、行政書士などの専門家から情報を得れば、見落としや誤解を防ぎ、最適な補助金を選ぶことができるでしょう。
書類作成
補助金申請では申請書だけでなく、事業計画書や収支計画書、見積書、契約書、経費証憑など、多くの書類を揃える必要があります。特にオフィス移転の場合、「移転によってどのように事業が成長するか」「業務効率がどう改善されるか」を具体的に示すことが求められます。単なる引っ越しの費用申請では採択されないケースがほとんどです。
書類作成にあたっては、情報の正確性や証拠の提示が重要です。見積書や契約書は正式な形式で用意し、経費証憑は日付や金額、内容が明確にわかるものを準備します。また、事業計画書では、移転の目的、経費の内訳、期待される効果、スケジュールを明確に記載することが求められます。
申請を行う
必要書類がすべて揃ったら、正式に補助金の申請を行う段階です。申請方法は制度によって異なり、オンライン提出や郵送、持参などがあります。
オフィス移転に関わる補助金は提出書類が多く、事業計画書や見積書、契約書、経費証憑に加え、場合によっては従業員の雇用計画書や教育訓練計画まで求められることがあります。
審査では、オフィス移転による業務効率化や売上増加、従業員の働きやすさ向上など、事業への具体的な効果などが評価の対象です。単に移転費用を補助してほしいだけでは採択されにくく、投資効果や計画の実現性を明確に示す必要があります。
申請期限も必ず守らなければならず、期限を過ぎれば書類の完成度が高くても採択対象外となるため、スケジュール管理は徹底しましょう。
補助金の受け取り
申請が採択されると、補助金の交付決定通知が届きます。多くの補助金は後払い方式で支給されるため、まずは自社で移転費用を立て替えて支払い、その後に交付手続きを進める必要があります。このため、申請時点で資金に余裕を持たせておくことが重要です。
交付手続きには、実績報告書や領収書、契約書の提出が求められます。書類に不備があると交付が遅れたり、金額が減額されることもあるため、正確に管理することが不可欠です。
補助金を受け取った後も、一定期間の事業報告や成果報告が義務付けられることがあります。報告を怠ると返還を求められる場合もあるため、管理体制を整えておきましょう。
補助金の受け取りまでの流れをスムーズにするには、申請前から書類整理やスケジュール調整を行い、交付後も証憑を適切に管理することが大切です。
オフィス移転ならヴォーエルへ!

オフィス移転は単なる場所の変更ではなく、事業成長や働き方改善の大きなチャンスです。しかし、移転にかかる費用は決して小さくなく、計画を誤ると資金繰りやスケジュールに大きな負担を与えてしまいます。
そこでおすすめなのが、オフィス移転専門のヴォーエルです。移転計画の立案から物件選定、内装工事、引っ越し作業までをワンストップでサポートし、補助金・助成金の情報提供や申請代行にも対応しています。これにより移転費用を大幅に抑え、確実な補助金受給が可能になります。
オフィス移転を検討中の企業は、ぜひヴォーエルのサポートを活用してください。