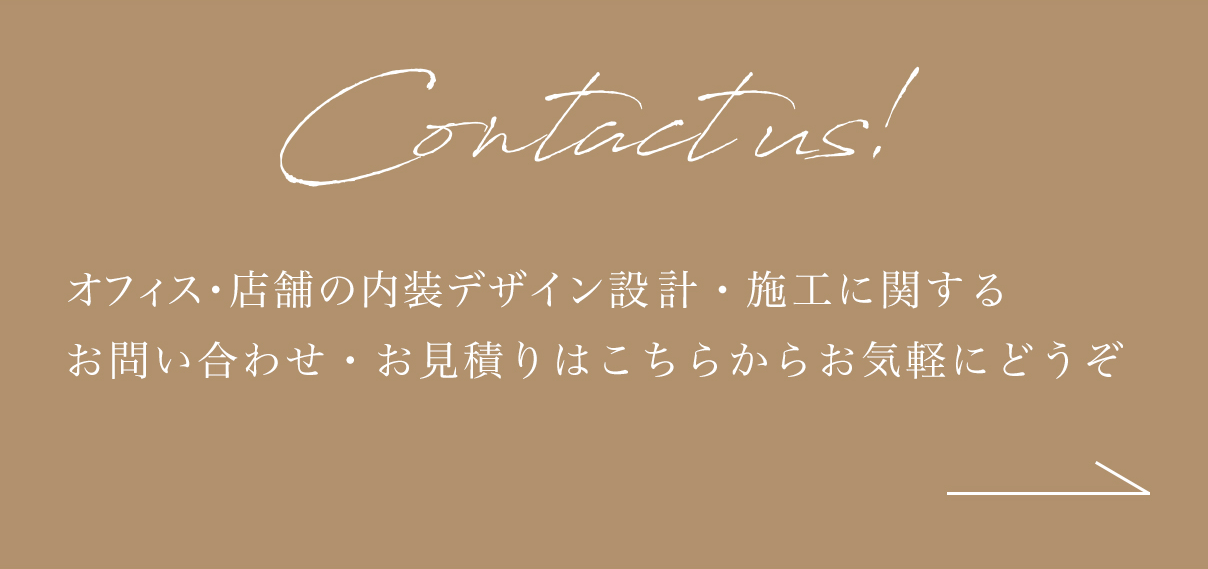オフィスの原状回復はどうすればいい?回復工程から注意点まで徹底紹介!

オフィスの移転や退去を控えている企業担当者にとって、原状回復は避けて通れない重要な手続きです。適切な知識がないまま進めてしまうと、予想外の高額請求や貸主とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
原状回復とは具体的にどのような工事を指すのか、費用相場はどの程度なのか、そしてどのような点に注意すべきなのかを正しく理解することが、スムーズな退去への第一歩となります。
本記事では、オフィスの原状回復に関する基礎知識から具体的な工事の流れ、費用の目安、さらにはトラブルを回避するための実践的な注意点まで、総務担当者が知っておくべき情報を徹底的に解説していきます。
適正価格で信頼できる業者に依頼するための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
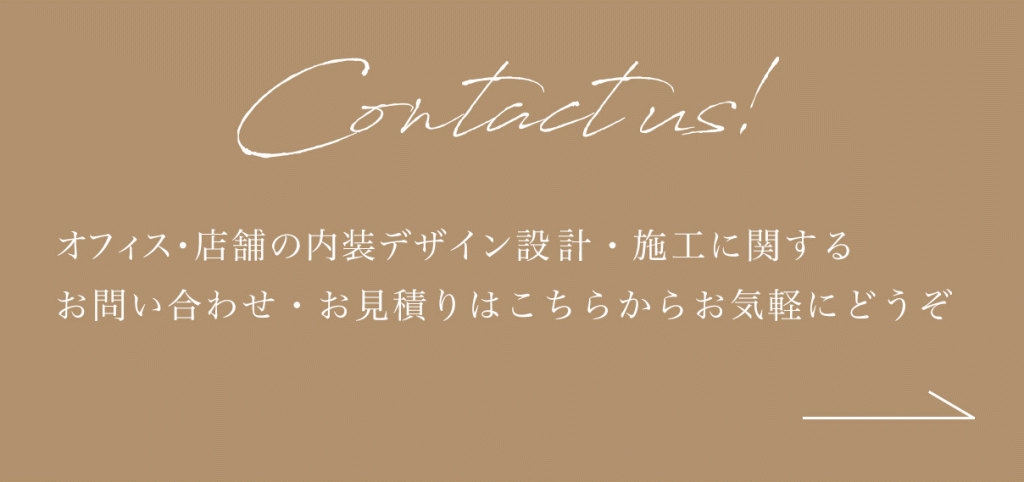
Index
オフィスの現状回復とは?

原状回復とは、賃貸オフィスを退去する際に、借りた時の状態に戻して貸主に返還する義務のことを指します。
これは単なる清掃やゴミの撤去だけでなく、内装や設備を契約開始時の状態に復元する工事を含む包括的な概念です。オフィス物件の場合、居住用物件とは異なる基準や契約内容が適用されることが多く、正確な理解が求められます。
ここでは、原状回復の法的な定義や適用範囲について、詳しく見ていきましょう。
国が定める現状回復
国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を
| 「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」 |
と定義しています。このガイドラインは主に居住用物件を対象としたものですが、基本的な考え方はオフィス物件にも参考とされることがあります。
ポイントは、経年劣化や通常使用による損耗については、原則として借主の負担範囲に含まれないという考え方です。壁紙の日焼けや、家具設置による床の凹み程度であれば、通常損耗として扱われる可能性があります。一方で、タバコのヤニによる変色や、不適切な使用による設備の破損などは、借主負担となるケースが一般的です。
ただし、このガイドラインはあくまで居住用物件を主眼としており、事業用オフィスには必ずしもそのまま適用されません。オフィス物件では、より厳格な原状回復義務が課されることが多く、契約内容によって大きく異なる点に注意が必要です。
国のガイドラインを理解しつつも、自社の契約書を確認することが最も重要と言えるでしょう。
民法621条による現状回復
民法第621条では、
| 「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う」 |
と規定されています。この条文が、賃貸契約における原状回復義務の法的根拠となっているのです。
2020年4月の民法改正により、原状回復に関する規定がより明確化されました。改正前は解釈に幅があった部分も、現在では「通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」という原則が明文化されています。これにより、借主と貸主の責任範囲がより明確になったと言えるでしょう。
しかしながら、事業用物件であるオフィスの場合、この民法の規定よりも契約書の特約が優先されるケースが多く見られます。特に「スケルトン状態での返還」など、通常損耗を含めた全面的な原状回復を求める特約が付されている場合は、民法の原則とは異なる義務が発生します。
法律の基本を理解しつつも、最終的には個別の契約内容が最優先されることを認識しておく必要があるのです。
現状回復の義務がない場合
原状回復義務が発生しない、あるいは軽減されるケースも存在します。
最も基本的なのは、通常の使用による経年劣化や自然損耗に該当する場合です。具体的には、日光による壁紙の退色、家具の設置跡程度の床の凹み、通常清掃していても発生する汚れなどが該当します。
また、貸主側の承諾を得て実施した設備投資や改装については、原状回復義務が免除される契約も存在します。テナント誘致のために貸主が「居抜き物件として次の借主に引き継いでよい」と認めた場合や、設備投資を歓迎する契約形態では、原状回復工事の範囲が大幅に縮小されるのです。
さらに、契約書に「原状回復義務を負わない」旨の特約が明記されている場合も該当します。ただし、オフィス物件でこのような特約が付されているケースは非常に稀です。むしろ、居住用物件以上に厳格な原状回復が求められることが一般的と考えておくべきでしょう。
自社の契約がどのケースに当てはまるのか、契約時から退去時まで常に意識しておくことが、トラブル回避の鍵となります。
オフィスの原状回復義務の範囲を解説!

原状回復義務の具体的な範囲は、一律に決まっているわけではありません。
契約内容や物件の種類、地域の商慣習などによって大きく異なるのが実情です。
ここでは、オフィス物件における原状回復義務の範囲がどのように決定されるのか、また特約の影響について詳しく解説します。理解を深めることで、退去時の想定外の出費を防ぐことができるでしょう。
契約の内容に応じて決定
オフィスの原状回復範囲は、まず第一に賃貸借契約書の内容によって決定されます。
契約書には原状回復に関する条項が必ず記載されており、これが借主と貸主の間で合意された法的義務となるのです。契約時に確認を怠ると、退去時に想定外の負担を強いられる可能性があります。
契約書で確認すべき重要なポイントは、「どの状態まで戻すのか」という具体的な定義です。「スケルトン状態」「躯体現し」などの用語が使われている場合、内装をすべて撤去し、コンクリート打ちっぱなしの状態まで戻す必要があります。
一方、「入居時の状態」という表現の場合は、既存の内装を活かした部分的な補修で済む可能性もあるのです。
また、契約書には原状回復工事を実施する業者の指定に関する記載も含まれることがあります。貸主指定業者での工事が義務付けられているケースでは、相見積もりの機会が制限され、費用が高くなる傾向があります。
契約段階でこれらの条件を十分に理解し、必要であれば交渉することが重要です。すでに契約済みの場合でも、改めて契約書を精読し、義務の範囲を正確に把握しておくことで、計画的な退去準備が可能になるでしょう。
原状回復工事に関する「特約」
オフィス賃貸契約において、原状回復に関する特約は極めて重要な意味を持ちます。
特約とは、民法や一般的な契約条件とは異なり、個別に定められた取り決めのことです。オフィス物件では、居住用物件よりも厳しい原状回復義務を課す特約が付されることが一般的と言えます。
代表的な特約としては、「スケルトン返還特約(スケルトン戻し、スケルトン返し)」が挙げられます。これは入居時に内装が施されていた場合でも、退去時にはすべて撤去して躯体だけの状態で返還する義務を定めたものです。この特約がある場合、天井や床、壁の仕上げ材、パーティション、照明器具など、ほぼすべての内装を解体・撤去する必要が生じ、費用が大幅に増加します。
その他の特約としては、「指定業者使用義務」「工事内容の事前承認」「退去立会いの詳細規定」などがあります。特に指定業者の使用を義務付ける特約は、競争原理が働かず高額になりやすいため、契約前に慎重な検討が必要です。ただし、事業用物件の契約では、借主側の交渉力が弱い場合も多く、貸主提示の条件をそのまま受け入れざるを得ないケースも少なくありません。
契約時に特約の内容を十分に理解し、退去時の費用を事前に見積もっておくことが、財務計画上も重要なポイントとなるでしょう。
オフィスの現状回復の目安となる費用とは?

オフィスの原状回復費用は、物件の広さや内装の程度、工事範囲によって大きく変動します。一般的な相場としては、坪単価3万円から10万円程度とされていますが、これはあくまで目安に過ぎません。
スケルトン返還が求められる場合や、特殊な内装を施していた場合は、坪単価15万円以上になることも珍しくないのです。
具体的な費用の内訳としては、内装解体工事、電気設備の撤去・原状復旧、空調設備の処理、床・壁・天井の補修、廃材処分費などが含まれます。特に廃材処分費は近年上昇傾向にあり、全体費用の20〜30%を占めることもあるため、見落とせない項目となっています。
また、アスベストを含む古い建材がある場合は、専門的な処理が必要となり、費用が跳ね上がる可能性があります。
面積別の具体例を挙げると、20坪のオフィスでは60万円〜200万円、50坪では150万円〜500万円、100坪では300万円〜1,000万円程度が一般的な範囲です。ただし、都心部の高級オフィスビルや、築年数の古い物件、特殊な内装を施していた場合は、これを大きく上回ることもあります。
自社のオフィスがどの程度の費用になるかは、早期に専門業者に相談して見積もりを取得することが最も確実です。退去の6ヶ月前には動き始め、複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格での工事実施が可能になるでしょう。
オフィスの現状回復までの工程を紹介!

原状回復工事は、いくつかの段階を経て進められます。
各工程を正しく理解し、適切なタイミングで必要な手続きを行うことが、スムーズな退去とコスト削減につながるのです。ここでは、契約確認から工事完了・引渡しまでの一連の流れを、時系列に沿って詳しく解説していきます。
契約内容の確認
原状回復の第一歩は、現在の賃貸借契約書を精査することから始まります。
契約書には原状回復の範囲、方法、期限などが明記されており、これが今後の作業の基準となるのです。退去を決定したら、まずは契約書を引っ張り出して熟読しましょう。
確認すべき主要項目は、原状回復の定義、工事範囲、指定業者の有無、解約予告期間、立会い規定などです。特に解約予告期間は重要で、多くのオフィス契約では6ヶ月前の通知が求められます。この期間を守らないと、違約金が発生したり、不要な賃料を支払い続けることになったりするため、注意が必要なのです。
契約書の内容が不明確な場合や、解釈に迷う表現がある場合は、早めに貸主または管理会社に確認することをおすすめします。書面での回答を求めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、入居時の写真や図面があれば、それらも併せて確認しておくと、原状回復の具体的なイメージが掴みやすくなるでしょう。契約内容の正確な理解が、その後の工程をスムーズに進める基礎となります。
業者に依頼
契約内容を把握したら、次は原状回復工事を実施する業者の選定に移ります。
契約書で業者が指定されている場合はその業者に連絡しますが、指定がない場合は複数の業者から選定することが可能です。業者選びは費用と品質の両面に大きく影響するため、慎重に進める必要があります。
業者選定のポイントとしては、原状回復工事の実績が豊富であること、見積もりが明瞭であること、対応が迅速かつ丁寧であることなどが挙げられます。
口コミや評判も参考になりますが、実際に問い合わせをして対応を確認することが最も確実です。また、工事保険に加入している業者を選ぶことで、万が一の事故やトラブルへの備えにもなります。
業者への依頼時には、オフィスの住所、面積、現在の内装状態、希望する工事時期などの基本情報を伝えます。可能であれば現地調査の日程を調整し、実際に物件を見てもらうことで、より正確な見積もりが得られるでしょう。
指定業者がある場合でも、その妥当性を確認するため、他の業者に参考見積もりを依頼することは有効です。ただし、最終的には契約内容に従う必要があるため、その点は十分に理解しておきましょう。
見積もり依頼
業者が決まったら、正式な見積もりを依頼します。
見積もりは単なる金額の提示ではなく、工事内容の詳細な説明を含むものであるべきです。優良な業者であれば、現地調査を実施した上で、項目別に細かく記載された見積書を提出してくれます。
見積書で確認すべきポイントは、工事項目の詳細、各項目の単価と数量、材料費と人件費の内訳、廃材処分費、諸経費の内容などです。「一式」という曖昧な表記が多い見積書は要注意で、後から追加費用を請求される可能性があります。不明な項目があれば遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることをおすすめします。
複数の業者から見積もりを取る場合は、同じ条件で比較できるように、工事範囲や仕様を統一して依頼しましょう。ただし、最安値の業者が必ずしも最良とは限りません。極端に安い見積もりは、工事品質の低下や後からの追加請求につながる恐れがあります。適正価格の範囲内で、実績と信頼性を重視して選定することが賢明です。
見積もりの段階で工事スケジュールも確認し、自社の退去予定日に間に合うかどうかも併せて検討しておきましょう。
工事開始
見積もりに合意し、契約を締結したら、いよいよ工事が開始されます。
工事開始前には、近隣テナントへの挨拶、工事スケジュールの最終確認、貴重品や重要書類の移動などの準備が必要です。特にビル全体に影響が及ぶ可能性がある場合は、管理組合やビルオーナーへの事前通知も忘れてはなりません。
工事中は、定期的に進捗状況を確認することをおすすめします。途中で問題が発見された場合は、早期に対処することで追加費用や工期の遅延を最小限に抑えられます。また、貸主や管理会社が中間検査を実施する場合もあるため、そのスケジュールも把握しておく必要があるのです。
工事期間中の注意点としては、騒音や振動による近隣への影響、共用部分の養生や清掃、廃材の適切な処理などが挙げられます。優良な業者であればこれらを適切に管理してくれますが、担当者として最低限の確認は行うべきでしょう。
万が一、工事内容に疑問や不安を感じた場合は、すぐに業者に確認し、必要であれば貸主にも報告することが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
工事完了引渡し
すべての工事が完了したら、最終検査と引渡しの段階に入ります。
この工程は原状回復プロセスの中で最も重要であり、ここで貸主の承認を得られなければ、追加工事が必要になる可能性があるのです。引渡しには、借主、貸主(または管理会社)、施工業者が立ち会うのが一般的となっています。
引渡し時には、契約書に基づいて工事が適切に実施されたかを確認します。
壁や床の仕上がり、設備の撤去状況、清掃の状態など、細部まで丁寧にチェックされます。この際、入居時の写真や図面があると、比較検討がしやすくなります。貸主から指摘があった場合は、その場で対応方法を協議し、必要であれば追加工事の実施を決定します。
引渡しが承認されたら、最終的な書類の取り交わしを行います。工事完了報告書や、原状回復完了確認書などの文書を受け取り、保管しておきましょう。これらは後日、万が一トラブルが発生した際の重要な証拠となります。また、鍵の返却や保証金の返還手続きについても、この段階で確認しておくことが大切です。
すべての手続きが完了して初めて、オフィスの退去プロセスが終了したと言えるのです。
現状回復の工事期間とは?

原状回復工事に要する期間は、オフィスの規模や工事内容によって大きく異なります。
一般的な目安としては、30坪以下の小規模オフィスで1〜2週間、30〜100坪の中規模オフィスで2〜4週間、100坪を超える大規模オフィスでは1ヶ月以上かかることも珍しくありません。工期を左右する主な要因は、解体する内装の量、特殊な設備の有無、廃材処分の規模などです。
特に、スケルトン返還を求められる場合は、天井や床、壁などをすべて撤去する必要があるため、通常の補修工事よりも時間がかかります。また、アスベスト含有建材がある場合は、専門業者による慎重な作業が必要となり、さらに工期が延びる可能性があるのです。
工事期間を短縮するためには、事前の準備が重要となります。オフィス内の荷物をすべて搬出しておく、工事に支障がない状態にしておくなど、業者が速やかに作業を開始できる環境を整えることが効果的です。
ただし、工期を無理に短縮すると、工事品質の低下や安全性の問題につながる恐れもあります。余裕を持ったスケジュールを組み、品質を優先することが、結果的に円滑な退去につながるでしょう。退去予定日の最低でも2〜3ヶ月前には工事計画を立て始めることをおすすめします。
オフィスの現状回復を行う際の注意点を解説!

原状回復工事を成功させ、トラブルを回避するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。これらを理解し、計画的に進めることで、コストを抑えながら円滑に退去を完了できるでしょう。
ここでは、特に重要な5つの注意点について、具体的に解説していきます。
指定業者以外に依頼できるか確認
多くのオフィス賃貸契約では、原状回復工事を実施する業者が貸主によって指定されています。指定業者制度は、ビルの統一性や品質管理の観点から設けられているものですが、借主にとっては選択肢が制限され、費用が高くなりがちな仕組みです。まずは契約書を確認し、業者指定の有無と条件を把握しましょう。
契約書に「貸主指定業者に限る」と明記されている場合でも、交渉の余地がある可能性はあります。特に、相見積もりの結果、指定業者の見積もりが著しく高額である場合は、その根拠を説明し、他業者の利用を認めてもらえるケースもあるのです。
ただし、このような交渉は時間を要するため、早めに動き始める必要があります。指定業者以外の利用が認められた場合でも、工事内容や品質基準については貸主の承認が必要です。
選定した業者の実績や保険加入状況を示し、適切な工事が実施されることを証明できれば、許可を得やすくなります。一方、指定業者の利用が絶対条件である場合は、その中で最もコストパフォーマンスの良い提案を引き出す交渉に注力することが賢明でしょう。
業者選定の自由度は、最終的なコストに大きく影響するため、契約時から意識しておくことが重要なのです。
工事の範囲を明確にする
原状回復でトラブルになりやすいのが、工事範囲の認識の相違です。「原状回復」という言葉の解釈が、借主と貸主で異なることが少なくありません。
退去時になって「ここまで戻す必要がある」と言われ、予想外の費用が発生するケースを避けるためには、事前の明確化をするほかありません。
工事範囲を明確にするためには、契約書の記載内容を基に、貸主または管理会社と具体的な打ち合わせを行いましょう。口頭での確認だけでなく、メールなどの文書で記録を残すことが重要です。
特に「スケルトン状態」「入居時の状態」などの曖昧な表現については、具体的にどの部分をどこまで戻すのか、写真や図面を用いて確認することをおすすめします。
また、入居時に貸主の承諾を得て実施した改装や設備投資については、原状回復の範囲から除外される可能性があります。このような特例についても、書面での証拠を残しておくことが大切です。
工事範囲が明確になったら、それを基に業者に見積もりを依頼し、貸主にも見積内容を事前に共有することで、工事完了後の「やり直し」を防ぐことができるでしょう。
退去日から逆算したスケジューリングをする
原状回復工事は、退去日までに完了していなければなりません。
工事が遅れると、追加の賃料が発生したり、次の入居先への移転に支障が出たりする可能性があるのです。確実に期日内に完了させるためには、退去日から逆算した綿密なスケジュール管理が必要となります。
理想的なスケジュールとしては、退去予定日の6ヶ月前に契約内容を確認し、4〜5ヶ月前に業者選定と見積もり取得を開始します。3ヶ月前には工事業者を決定し、2ヶ月前から荷物の搬出や事前準備を進めるのです。
そして退去日の1ヶ月半前には工事を開始し、余裕を持って完了させることが望ましいでしょう。
スケジュールを立てる際には、予備日を必ず設定しておくことが重要です。想定外の問題が発覚して追加工事が必要になったり、天候や資材調達の関係で工事が遅延したりする可能性があります。ギリギリのスケジュールではこうしたリスクに対応できないため、最低でも1〜2週間の余裕を見込んでおきましょう。
また、定期的に進捗を確認し、遅れが生じた場合は早期に対策を講じることも大切です。
閑散期を狙う
原状回復工事の費用や工期は、時期によって変動することがあります。
特に2〜4月、9〜10月は企業の移転が集中する繁忙期であり、工事業者のスケジュールが埋まりやすく、費用も高めに設定されることが多いです。可能であれば、これらの繁忙期を避けて工事を実施することで、コストと品質の両面でメリットが得られます。
閑散期である5〜8月、11〜1月に工事を依頼すれば、業者にも余裕があるため、丁寧な対応や値引き交渉の余地が生まれやすくなります。また、人材や資材も確保しやすく、予定通りの工期で完了する可能性が高まるのです。繁忙期に比べて10〜20%程度のコスト削減が期待できるケースもあります。
ただし、閑散期を狙うためには、退去時期をある程度コントロールできることが前提となります。
解約予告期間や新オフィスの入居時期との兼ね合いもあるため、すべての企業が閑散期を選べるわけではありません。可能な範囲で時期を調整し、少しでも有利な条件で工事を実施できるよう計画することが重要です。
移転計画を立てる段階から、原状回復工事の時期も含めて総合的に検討することで、全体のコストを最適化できるでしょう。
補助金を活用する
原状回復工事そのものに対する補助金は一般的ではありませんが、関連する費用について支援制度が利用できる場合があります。
特に、移転に伴う新オフィスの内装工事や設備投資に対しては、自治体や国の補助金制度が用意されていることがあるのです。これらを活用することで、トータルでの移転コストを削減できる可能性があります。
例えば、働き方改革や環境配慮型オフィスへの移転を支援する制度、中小企業の生産性向上を目的とした設備投資補助金などが該当します。
また、省エネルギー設備の導入に対する補助金や、テレワーク環境整備のための支援制度なども、新オフィスの設計次第では活用できるでしょう。各自治体の商工会議所や中小企業支援センターに問い合わせることで、利用可能な制度を確認できます。
補助金の申請には一定の要件があり、事前申請が必要なケースがほとんどです。工事着工後では申請できない制度も多いため、移転計画の初期段階から情報収集を始めることが重要となります。申請書類の作成や審査には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
直接的な原状回復費用の削減は難しくても、移転全体のコストを抑えることで、実質的な負担軽減につながるのです。
オフィスの現状回復に困った時はヴォーエルへ相談!

オフィスの原状回復工事は専門性が高く、経験豊富な業者に依頼するのがおすすめです。
ヴォーエルは、オフィスの原状回復から内装工事まで幅広く手がける、空間づくりの専門企業です。賃貸オフィスの原状回復に関する豊富な実績を持ち、契約内容の精査から工事完了まで、一貫したサポート体制を整えています。
貸主との交渉経験が豊富であり、適正な工事範囲とコストでの原状回復を実現できる点も強みです。契約書の内容を丁寧に確認し、必要な工事と不要な工事を明確に切り分けることで、無駄なコスト削減を実現しています。
施工後のアフターフォローも充実しており、万が一貸主から指摘があった場合も迅速に対応します。
オフィスの原状回復でお困りの際は、まずヴォーエルの公式サイトからご相談ください。経験豊富なスタッフが、円滑な退去を全面的にサポートします。